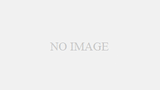70年代の中頃、ニューヨーク市ブロンクスのDJを中心とした若者たちが新しい表現様式を発信しはじめる。
これが熟成して形を成すのが70年代の後期で、世界的なディスコ・ブームの頃だ。すでに産業として巨大化したディスコは事業の多様化を探っていた。こうした時代の風潮とは離れ、ブロンクスに住む若者たちは純粋にビートの進化や表現手法にこだわる。街角/ストリートから発信するそれをヒップホップと呼んだ。
ヒップとホップ、この造語の語源や意味は現在まではっきりと定義されていないが、新しくて格好良く(Hip)躍動(Hop)するという意味合いと推測出来る。
街角の壁などをキャンバスにスプレー缶で描かれる/グラフィティ(Graffiti)。
DJは数小節のブレイクビーツ(Break Beats)をくり返し/ループ(Loop)させ、レコード盤を擦る音/スクラッチ(Scratch)を操る。
そのリズムで韻(Rhyme)をふみ、喋る/ラップ(Rap)。
そして、路上に段ボールなどを敷いてつくられたダンススペース。ダンサーたちはDJが発するリズムにいままでに無いムーヴのブレイキン(Breakin’/ブレイクダンスと記しているケースも多いが正確にはブレイキン)で応える。
このグラフィティ、DJ&スクラッチ、ラップ、ブレイキンの4要素がヒップホップと定義されている。
1979年、シュガーヒル・ギャングというグループの『ラッパーズ・ディライト』というラップ曲が大ヒットする。この曲がラジオやディスコで頻繁にかけられたことでヒップホップとラップの存在が一般社会でも認識された。